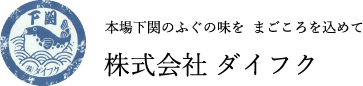ふくのはなし
伊藤公はふぐびいき
「ふぐは食いたし命は惜しし」、「真に一死に値する」といわれるふぐの味。
江戸時代の俳人・一茶や芭蕉もふぐをよんだ句がいくつかあり、そのうまさに魅かれて、さかんにふぐを食べている。
豊臣秀吉によって、わが国で最初のふぐに関する禁止令が出され、江戸期になるとあちこちの藩で禁令が出されるようになり、黒田藩や長州藩ではふぐを食べ中毒死した場合はお家断絶と、武士にとって最高の厳罰が設けられた。明治になってからも「ふぐを食う者は拘留科料に処する」という禁令があった。
明治21年、22年の頃、すでに伯爵になっていた伊藤博文が下関に来て、春帆楼に遊んだが、あいにくその日はしけで魚がない。女将がその旨を申し上げると「俺はよいが、馬関(下関)に来て魚がないとは…。」とやんわり皮肉った。女傑として名高い女将が、それではと意を決して禁令のふぐを出したところ、こんなうまいものを食べない法はないと、早速、時の山口県令・原保太郎に命じて、その項を削らせたという。下関にとってはまさに「伊藤博文様々」なのです。
珍味中の珍味 ふぐの白子
ふぐの白子は昔から「西施乳」(西施とは、中国の春秋時代の傾国の美女)の異名を持ち、これをふぐの最大の妙味とする人も多い。白子酒は、ふぐの白子(精巣)を湯通しして、それを酒に入れて微妙な味わいをたんのうするものです。
ふぐの刺身をつまみ、ほどよい燗の地酒に西施乳を溶かして口に含めば、酒好きならずとも夢幻の味の世界に惹き込まれてしまうのです。
志士が広めたふぐ刺しの味
ふぐが刺身として食べられ初めたのは意外と時代が下ってからのことでした。
幕末下関で活躍した高杉晋作等の志士たちが食べ始めたと推定されています。
そしてこの志士たちが全国を奔走した結果、この美味の宣伝に力を借したのかもしれません。
テトロドトキシン
フグの毒はテトロドトキシンという猛毒です。そのためフグ中毒によって昔からたくさんの人が亡くなっています。現在でも毎年数十件のフグ中毒が発生しており、特に多いのが営業施設以外(家庭等)で自家調理したものの事故です。
フグには、種類によって食べられるものと食べられないものがあり、そして食べられる種類のフグでも食べられる部分とそうでない有毒な部分があります。有毒部分は完全に除去しなければならないため、都道府県で認可したフグ処理師の資格や加工処理施設などが必要です。
料理の用語で「魚を三枚に下ろす」といいますが、フグの場合その前にさらに1次加工が必要で、これを「身欠き」といい極めて専門性の高い特殊な加工技術です。この過程で有毒部分を除去しすべてを食べられるようにするのです。
身欠きされたフグは三枚に下ろし刺身やちり用として加工されますが、1匹のフグを処理するのに30リットル近い水を使用します。水をふんだんに使って処理するからこそフグは安全なのです。お客様が調理されたフグを口にするまでにはたいへん長い過程を経てきているのです。
手と手をつなぐ袋セリ
下関唐戸市場のセリといえば「袋セリ」で有名です。「ふぐセリ」ともいわれるこの「袋セリ」は、もともと冬場の市場の寒さをしのぐために着ていた合羽の袖口のなかで、手を入れて指を握ってせっていたものが、戦後その袖口の広い合羽の代わりに、ひじから先の長さの黒い袋を使ったのが現在の袋セリの原型だそうです。
「エカエカエカ…」(「用意はいいか」「場を締めてもいいか」の意)というセリ人の掛け声に合わせて仲卸人は黒い袋の中に手を入れ、セリ人の指を握り提示額を示すのです。この下関独特の「袋セリ」によって、瞬時にふぐの値打ちを見極め目当てのふぐを獲得しなければならないセリは「闘い」の場です。
ふぐの延縄漁法
高級食材となるトラフグは最高の鮮度が求められることはもちろん、体に傷がついても活魚としての価値が下がってしまうため、延縄漁法で獲られたものが尊ばれます。
同じトラフグでも網漁法で獲られたものは衰弱やストレスによる鮮度の低下が著しくその価値は半減します。
現在の延縄漁法は山口県徳山市沖に浮かぶ粭島(すくもじま)の漁師によって考案されました。釣り針や幹糸をふぐの歯で切られるのを防ぐため、部分的に鋼線を使用するなどの改良が重ねられていき、それが今日のふぐ延縄の基礎となったのです。
粭島では昔から「ふぐはお姫様のように扱え」という口伝が残っています。それが粭島の漁師の伝統であり、ふぐ延縄漁法を専門としている漁師気質でもあるのです。
ふぐとコラーゲン
ふぐの皮にはコラーゲンが多く含まれています。コラーゲン(膠原質)は動物の結合組織の基礎となる蛋白質ですから、これを食べると身体の強化に役立ち、つやのある髪、澄んだ瞳をつくるといわれます。そのため化粧品の製造にも応用されています。
またコラーゲンは消化吸収もよく、他の栄養分を長く体内に引き止めておくという効果もあります。このように皮は良質の蛋白質であるコラーゲンを多く含み、栄養的にも優れた食品だといえます。
ちなみにコラーゲンは普通の状態では繊維状であるため水に溶けないのですが、加熱すると分解し、ゼラチンとなって水に溶ける性質を持っています。これを冷やしゼリー状に固めるとふぐの煮こごりができるのです。
ふぐの禁止令の始まり
豊臣秀吉は朝鮮征伐のために肥前の国に名護屋城を築城しここを基地に16万の兵を全国から駆り集めた後、朝鮮へ出兵させました。これが文禄の役(1592年)です。
この用兵を全国から集めているときに、禁止令の契機となる事件が持ち上がったのです。朝鮮出征の際、一旦下関へ集結した兵たちは諸国から来ているのでふぐの毒を知らず内臓も煮て食べて命を落とす者が続出しました。
そこでたまりかねた秀吉は町の辻つじに禁札を立てさせ、これにふぐの絵を描いて「この魚食うべからず」とその食用を禁じたのです。これがわが国におけるふぐ中毒取締令の始まりなのです。
ふぐを詠んだ俳句
ふぐは冬の季語になっており、古くから多くの俳人がふぐに関する句を詠んでいます。
高名な俳人である松尾芭蕉は「ふぐ汁や鯛もあるのに無分別」「あら何ともなやきのふは過ぎてふぐ汁」といった句を残していますし、小林一茶は「ふぐ食わぬ奴には見せな富士の山」「五十にて鰒との味を知る夜かな」と詠んでいます。
武士階級の出である芭蕉がふぐに対して冷淡であるのにくらべ、一茶はふぐの味を賞賛しているのが興味深いところです。
これは江戸時代に侍がふぐを食べることが禁忌とされていたことと無縁ではないと思われます。
ふぐの川柳
ふぐは滑稽や諧謔を特徴とする川柳にとって格好の題材でした。これは恐ろしい毒を持ちながらも容姿がどこかユーモラスであることやその味が古くから食通に絶賛されてきたことに原因がありそうです。
ふぐの毒に関するものとしては「恐ろしきものの喰いたや雪のそら」「臆病は葱ばかり食う雪の夜」などがあり、食通を揶揄したものとして「ふぐ通といわれる馬鹿は肝も食い」が残されています。
ふぐの王
フグの仲間は現在では100種類以上いることがわかっていますが、食用とされるのは20種類程度です。
その中でもトラフグはいうまでもなく最も高価で美味とされています。
外見的な特徴としては背面は青色みがかった黒色をしており、背面、腹面には小棘が密生しています。
胸ひれの後ろに大きい斑紋があり、体長は70㎝以上に達するものもあります。
斑紋がトラを連想させるためトラフグの名がありますが、地方によってはシロ、オオフグ、ホンフグ、マフグ等の名で呼ばれています。
生息地としては北海道南部から中国沿岸まで広く分布していますが、瀬戸内海西部産のものが最も美味といわれます。
肉、精巣(俗にいう白子)、皮は食用とされますが、卵巣・肝臓には1匹で十数名を殺すほどの毒(テトロドトキシンTetrodotoxin)を持っています。
ちなみに「Tetrodotoxin」のTetrは4、odoは歯、toxinは毒素を意味し、マフグ科に属する魚は上下2本計4本の歯を持つことから名づけられたマフグ科の学名(Tetraodontidae)に由来します。
ふぐの日
日本には様々な記念日が設けられていますが、ふぐに関する記念日もあります。
下関ふく連盟は昭和55年、「ふぐ」の語呂に合わせて2月9日を「ふぐの日」に制定しました。毎年この日には下関市南部町の恵比寿神社で、豊漁と航海安全を 祈願する「ふぐ祈願祭」が行われます。この後市内の養護老人ホームへふぐ刺し慰問することが年中行事になっています。
また、「ふぐの日」に関連して11日には,「ふぐの日まつり」も下関彦島の南風泊市場で開かれています。消費者にふぐを安く還元する趣旨で平成9年から行われるようになりました。毎年恒例となっている無料の「ジャンボふぐ鍋」やふぐ刺しを始めとするふぐ関連製品の即売、オークション、料理教室などのイベントが行われ,毎年大勢の人でにぎわいます。お近くの方は是非一度足を運ばれてみてはいかがでしょうか。
ふぐの呼び名
ふぐは非常に多くの異名を持つ魚である。
比較的よく知られた呼び名としては ふく、ふくべ、ふぐと、てっぽう、とみ、きたまくら、がんばなどがあげられる。
古くは海底の砂を吹いて餌を取る姿から、ふく(吹く)と呼ばれていた。又ふぐの本場下関ではふぐは不遇に通じるというので縁起を担いでふく(福)とにごらずに呼ばれることはよく知られている。ふくべとはひょうたんのことで 膨らんだ様子がひょうたんを連想させるからであろう。
とみ、てっぽう、きたまくら、がんばはふぐの毒に由来する呼び名である。まず、とみであるが富くじの略語で、滅多に当たらないの意。
異名としては最も有名と思われるてっぽうは 当たると死ぬから、または滅多に当たらないという喩えからきている。これはふぐ食がご法度の頃に関西で使われていた隠語がそのまま定着したものである。略して「てつ」ともいう。
きたまくらはいうまでもなく死者の北枕のことであり、がんば(棺ば)は棺おけのこと。
いずれもふぐの毒に当たると死を招くことに由来する。
ふぐの由来
河豚(ふぐ)の古名はふくであり「東雅」には、ふくとはその腹脹れることをいうと記されています。要するにその語源は怒ると腹がふくれることによるのです。
また一説によればふくは海底の砂を吹いて出てくるゴカイ類を食べる性質があるので「吹く」に由来するとも言われています。
とおとうみ
一般に食べられている「とらふぐ皮」はとらふぐの本皮と内皮をボイルして細切りにしたものです。通の中には刺身よりもむしろ皮の方を好まれる方もいらっしゃるようです。
本皮は透明感があってコリコリした歯ごたえのある皮で、一般にふぐ皮というとこちらを思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。
内皮はふぐの身と本皮の間にあるゼラチン質の部分で、ふぐの業界では「遠江(とおとうみ)」という符牒で呼ばれています。
本皮のようなコリコリ感はありませんが、身に近い分、旨味は遠江の方があります。
ちなみに、遠江は旧国名で現在の静岡県の西部にあたります。
どうしてふぐの内皮を遠江と呼ぶのかというと、身と皮のそば、つまり三河のそばにあるという洒落からきているようです。